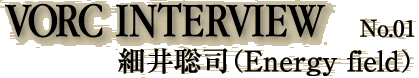
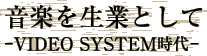
▼仕事として最初に手がけた作品は何でしょうか?
▼NEOGEO時代の制作環境はX68000のZ-MUSICだったと聞いています。特殊な例だと思うのですが、なぜこの環境で制作することになったのでしょう?
もともとMIDIで制作する開発環境がありましたが、発音数の少ない当時の音源の場合、MMLでの特殊な打ち込み技術が不可欠と判断し、新人のプログラマーさん一人サウンド専任にしてもらい、一から開発環境を作り直しました。今思えばなんて生意気な新入社員だったんでしょう。ほんと好き勝手やらせてもらって、上司の方には感謝しています。
▼パワースパイクス2とソニックウイングス2は、NEOGEOには稀に見る、音源スペックを使いきった作品だったと思います。PSG, FM, PCM…性格の異なる三種類の音源を同時使用するうえで、気をつけたことや苦労したことはありますか?
FM4声をどう使うかはかなり悩みました。実はこの辺の作品はまだ模索中という感じなんですが。
FMの音色作成はほとんどぴろを氏によるものです。彼なしでは全ての作品はあり得ませんでした。効果音の多くも彼ですが、特に緋炎のボムレーザーの音はすごいです。FMでここまで出来るのかと思いました(実際はX68000のFM8声で作ってPCMにサンプリング)。
NEOGEOの大容量にものをいわせてフレーズサンプリングを多用することも出来たのですが、あまりPCMに頼りすぎないようにしたのがむしろよかったのかも知れません。というと聞こえがいいですが、X68000を開発マシンにしていた都合上、あまりたくさんのPCM容量を使えなかったというのが実状です。
ちなみに「ソニックウイングス2」のボス曲ではピアノにフレーズサンプリングを使っています。ぼくの中ではシューティングゲームのボス曲のチャンピオンは「グラディウス」なんですが、それを超えようという意図のもとに制作しました。「妙な違和感」を感じていただければ幸いです。
PSGの使いどころはかなり悩みました。どうしてもそこだけ異質になってしまうので、もう割り切って異質にしたいところで使っています。「ソニックウイングス2」でPSGノイズを使っている曲が1つだけあるのですが、「スペースハリアー」のボス曲へのオマージュだったりします。
FMの音色作成はほとんどぴろを氏によるものです。彼なしでは全ての作品はあり得ませんでした。効果音の多くも彼ですが、特に緋炎のボムレーザーの音はすごいです。FMでここまで出来るのかと思いました(実際はX68000のFM8声で作ってPCMにサンプリング)。
NEOGEOの大容量にものをいわせてフレーズサンプリングを多用することも出来たのですが、あまりPCMに頼りすぎないようにしたのがむしろよかったのかも知れません。というと聞こえがいいですが、X68000を開発マシンにしていた都合上、あまりたくさんのPCM容量を使えなかったというのが実状です。
ちなみに「ソニックウイングス2」のボス曲ではピアノにフレーズサンプリングを使っています。ぼくの中ではシューティングゲームのボス曲のチャンピオンは「グラディウス」なんですが、それを超えようという意図のもとに制作しました。「妙な違和感」を感じていただければ幸いです。
PSGの使いどころはかなり悩みました。どうしてもそこだけ異質になってしまうので、もう割り切って異質にしたいところで使っています。「ソニックウイングス2」でPSGノイズを使っている曲が1つだけあるのですが、「スペースハリアー」のボス曲へのオマージュだったりします。
▼細井さんがVIDEO SYSTEMで活躍した1990年代前半から中盤にかけては、ゲームミュージックというジャンルにとって激動の時代だったと思います。やがてナムコの「リッジレーサー」のように、既存のゲームミュージックと接点のない音さえ「ゲームミュージック」と呼ばれるようになります。細井さんはしかし、それまでのゲームミュージックと絶妙のバランスを保ちつつそういう要素を取り入れていったという印象を持っています。当時のchip音源の衰退とサンプリングの隆盛、テクノ/ハウス/ドラムンベースといったクラブミュージックの発展などからどういう影響を受けましたか?
「リッジレーサー」は結構好きだったりします。ドライブゲームのBGMとしてはかなり気持ちいいですね。細江慎治さんも楽器が弾けないとどこかで仰っていたと思うのですが、妙に親近感が沸きました。クオリティの差はともかくとして、作曲のプロセスや感性は似ているような気がします。
「ソニックウイングス3」の全編JUNGLEはぴろを氏のアイディアです。当時はダンスミュージック嫌いでしたが、JUNGLEは好きになりましたね。
「ソニックウイングス3」の全編JUNGLEはぴろを氏のアイディアです。当時はダンスミュージック嫌いでしたが、JUNGLEは好きになりましたね。
▼要所要所で名前が出てくるぴろをさんですが、ここでどういう方なのか、詳しく教えていただけますでしょうか。
中学生くらいから一緒につるんでいた友達です。中学3年生の時、彼の持っていたPC-88で共同制作した「YM2203」というテープ作品を音楽の先生に聞かせたところ「君こんなことやってたのか」と驚かれました。そん時に誉めてもらったのがその後の自信に繋がったりして、今でもその先生には感謝しています。その後二人ともX68kに移行し、ビデオシステムへと繋がっていきます。
共同制作の場合、彼が音色や個性的なフレーズを作り、ぼくがそのフレーズを拝借して曲にまとめたりアレンジしたりといったパターンが多かったと思います。
今でもたまにメールで、なんか作りたいねーなどと言っている、ぼくの数少ない友達の一人です。
共同制作の場合、彼が音色や個性的なフレーズを作り、ぼくがそのフレーズを拝借して曲にまとめたりアレンジしたりといったパターンが多かったと思います。
今でもたまにメールで、なんか作りたいねーなどと言っている、ぼくの数少ない友達の一人です。
▼VORCの知る限りの細井さんの関わった作品のリストは以下のものなのですが、これ以外にも担当作品はありますでしょうか? また自分のお気に入りや印象深い作品があればそれも教えてください。
F-1グランプリPart II(AC/93)、タオ体道(AC/93)、パワースパイクス2(AC/94)、ソニックウイングス2(AC&NGCD/94)、ソニックウイングス3(AC/95)、対戦アイドル麻雀ファイナルロマンス2(AC/95)、対戦麻雀ファイナルロマンスR(AC/95)、ソニックウイングスリミテッド(AC/96)、ソニックウイングススペシャル(SS/96)、バーミリオンデザート(DC/99)、降魔録(PC/01)、世界ノ全テ(PC/02)、Reflective Heart(PC/02・春発売予定)、白詰草話(PC/02・7月発売予定)※AC:アーケード、NGCD:NEOGEO CD、SS:SEGA SATURN、DC:Dreamcast、PC:パソコン
よく調べましたね(笑) その他ではAC「爆裂クラッシュレース」、SFC「闘牌伝」、N64「麻雀道64」をやりました。最近ではPS2「スマッシュコート プロトーナメント」に2曲ほど提供しています。
「闘牌伝」は、この頃の作品はほとんどそうですがぴろを氏との合作です。これでもかというくらい自分の好きな音楽をやってます。ライヒ、上野耕路さんなどの影響が色濃く出てます。もうパクりかというくらい。でも今でも好きな作品の一つです。
「爆裂クラッシュレース」は最初「アウトラン」のように最初から最後までノンストップで流れる5分ほどのBGMにしていたのですが、途中でゲームの仕様が変わってステージが細かく区切られることになり、全曲作り直しになりました。ほろ苦い思い出です。幻の最終ステージBGMには歌詞があって、SC-88でカラオケ作ってカラオケBOXで歌ったりまでしてたんですが。
あとはやはり転機となった「降魔録」は非常に感慨深いものがあります。Energy fieldとしての最初の仕事です。相当気合い入っていましたが気負い過ぎず、いいバランスで制作できたなと思います。18禁という限られた市場なのが残念です。
「闘牌伝」は、この頃の作品はほとんどそうですがぴろを氏との合作です。これでもかというくらい自分の好きな音楽をやってます。ライヒ、上野耕路さんなどの影響が色濃く出てます。もうパクりかというくらい。でも今でも好きな作品の一つです。
「爆裂クラッシュレース」は最初「アウトラン」のように最初から最後までノンストップで流れる5分ほどのBGMにしていたのですが、途中でゲームの仕様が変わってステージが細かく区切られることになり、全曲作り直しになりました。ほろ苦い思い出です。幻の最終ステージBGMには歌詞があって、SC-88でカラオケ作ってカラオケBOXで歌ったりまでしてたんですが。
あとはやはり転機となった「降魔録」は非常に感慨深いものがあります。Energy fieldとしての最初の仕事です。相当気合い入っていましたが気負い過ぎず、いいバランスで制作できたなと思います。18禁という限られた市場なのが残念です。
▼なんと。もしかすると、ご自身の歌声がゲームセンターに響き渡っていたかもしれないのですか?
いや、単に個人的な趣味で歌詞付けたりカラオケ作ったりしていただけです。思いっきりタ○ムボカン風を狙った曲調だったり、それまでのステージBGMがメドレーで復活したりと、なかなかに楽しい曲でした。歌声は聞けませんが、ゲームのタイトルコールはぼくの声です。エンディングで叫んでいるのもぼくやぴろを。その他にも「タオ体道」のヒューイの声や、ソニックシリーズのボス登場前の台詞なんぞをやっておりました。昔は良くも悪くも手作り感覚だったんですね。
▼なるほど。ところでソニックウイングス2についてお聞きしたいのですが、NEOGEO CD版は内蔵音源の曲を大幅にアレンジしてあります。CDに収録されたものを見ると『NEO・GEO CD Ver.Arranged by NAOKI ITAMURA(VIDEO SYSTEM』と表記されていますが、これは細井さんが関わっていないということでしょうか?
主に関わったのはぼくと上司(後に「ソニックウイングススペシャル」のオープニングを作曲)、それから謎のアルバイトの3人で、「フランスステージ」や「テヌキーチャウド」などはぼくが担当しました。タイトなスケジュールではありましたが、アレンジバージョンにこれだけ時間を割くことが出来たのは後にも先にもこれ限りで、非常に楽しく作業させてもらいました。
3人の合作である「メキシコステージ」「オーストラリアステージ」が一番気に入ってます。「メキシコ」に入っている声は自前です。サントラ収録時、レコード会社の方が「オーストラリアステージ」をいたく気に入られたようで、CDの中でこれだけ2ループしてます(^^;
3人の合作である「メキシコステージ」「オーストラリアステージ」が一番気に入ってます。「メキシコ」に入っている声は自前です。サントラ収録時、レコード会社の方が「オーストラリアステージ」をいたく気に入られたようで、CDの中でこれだけ2ループしてます(^^;
(続く)
[HOME]
あと同時に「ソニックウイングス」のデータ作成(楽譜からの打ち込み)にも参加しました。